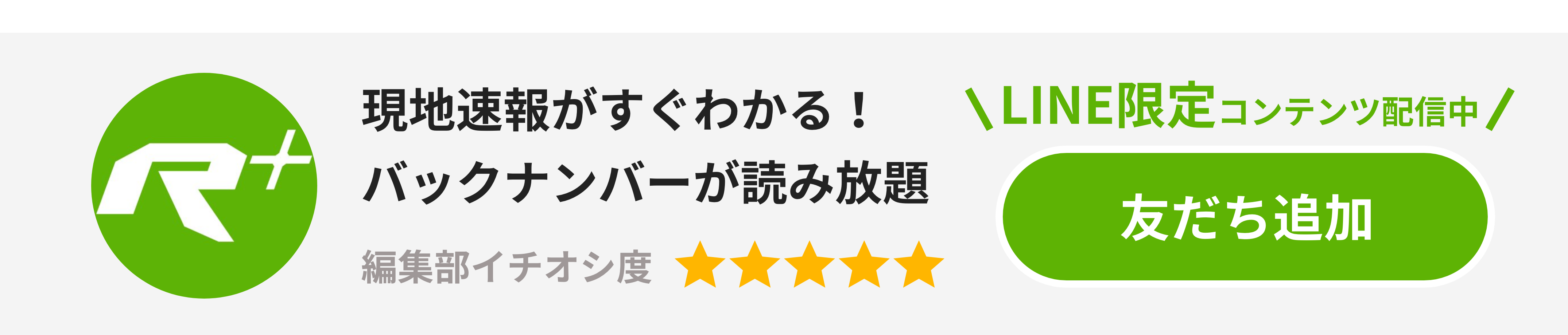©RALLYPLUS
トヨタ・ガズーレーシング(TGR)は、日本人若手ドライバーの発掘・育成を目的としたTGR WRCチャレンジプログラムの5期生となるドライバーの国内実技二次選考を9月19日、愛知県の幸田サーキットで実施。定員いっぱいの100人の応募のなかから、91人が1次選考に参加。そこから選出された19人が二次選考に参加し、5人のファイナリストが選出された。12月には、MORIZO Challenge Cupでチャンピオンとなった大竹直生とともに、フィンランドで実技トレーニングを行い、最終的に5期生となるドライバーを決定する。
この選考会を終えて、ドライビングのインストラクターを務めるミッコ・ヒルボネン、ヨウニ・アンプヤに5回目となる選考について聞いた。
──今回の5期生国内最終選考には91人が参加し、2次選考には19人が進出。とても盛況だ。今回の選考会での印象は。
ミッコ・ヒルボネン(MH):今日の選考を終えて、フィンランドの最終選考に進出されたメンバーは、今回もとても頼もしい顔ぶれになったと思っている。一週間の作業を終えて、個人的な意見ではここ2年間よりも、モータースポーツの経験をあまり持っていない応募者が増えたように感じた。でも、TGRとしては、このプログラムやこの場所を、誰もがチャンスが得てキャリアを始めるきっかけにしてもらいたいと願っており、未経験の応募者がクルマに乗ってどんなレベルやスキルを持っているのかを見たいと思っている。だから、未経験者の応募が増えたのは悪いことではない。今年、何か違いを感じるとすれば、その点だ。
──今回は、選考で使用する車両にトヨタGR86を使用した。その理由は。
ヨウニ・アンプヤ(JA):何かを変えたいと思っていた。ここ2年は国内選考を富士スピードウェイでやっていて、同じサーキット、同じようなマシンが続いていた。応募者のなかにも、2回目、3回目の参加になる者も出るようになってきたので、コースや車両を変えて、誰にでも新しい要素があるなかでの力量を見たかった。どちらも、うまくいったと思う。今年の選考にすごく合っていたし、迅速に切り替えられたということだ。
MH:それに、GR86は、パワーの面でドライビングが少し難しいと思うので、ドライバーの違いを見ることもできる。マシンがスライドし始めた時やアンダーが出た時に、対応できるか、どのような走りをすればいいのかをドライバーたちが理解しているかどうかが、分かりやすくなる。
──二次選考では、走行が始まった時点では一時的に強い雨が降り、順番が後になるにつれて路面もドライになっていった。この状況で、どのように審査をするのか。
MH:本当は、一日を通して雨が降ってくれることを期待していた。雨になれば、ドライバーたちにとっては、よりチャレンジングになる。丁寧に走らなくてはならないし、グリップの限界を見極めて、アンダーステアやオーバーステアになった時にはマシンをコントロールしなくてはならない。でも、天気はどうにもならないからね。いずれにしても、ウエットを走ったドライバーのことも、ドライを走ったドライバーのことも、その違いを見ることはできる。
ヨウニ・アンプヤ(JA):ウエットを走ったドライバーについて、我々はタイムだけでなく、グリップレベル、フィーリング、マシンの挙動等のメモを取った。ドライバーたちのことを見るためには隣に乗る以外に方法はないと思っている。コンディションが違うことで我々が迷うことはない。
──今年は、フィンランドでのファイナル選考への進出者は5人と、前回よりもひとり少ない。何か具体的な理由はあるか。
MH:特にはない。最もポテンシャルがあると感じられたドライバーを選んだだけだ。選出した5人と、それ以外とでは、ある程度の差を感じられた。
JA:5人以外のドライバーに対しては、フィンランドでのトレーニングのような機会を得る前に、もっと練習やトレーニングが必要だと感じた。5人については、みんな同等に、力量を感じられるメンバーになった。
──5人のうち4人はラリーの経験があるが、高岡は経験がない。彼からは、どのようなポテンシャルが感じられたか。
JA:フィンランドのトレーニングでは、もっと長い時間を一緒に過ごして、別の車両での走りも見ることができるので、その成長過程を見ることになるが、経験の少ないドライバーは成長やスキルを伸ばす伸び代がより多い。だから、どう学ぶか、どのように変化していけるか、それは全員に対して見ていくわけだが、その点について興味深かった。フィンランドでは、彼はほとんど経験がないはずの雪での走行をすることになるが、成長する余地が大いにあると思っている。
MH:二次選考で、彼はウエットコンディションでの走行になったが、生まれつきクルマの操縦スキルを持っていると感じられた。その意味では才能を見ることができた。それが一番だった。例えば、ベースに何を持っているかは関係なく、学ぶことができるかどうか。才能やそうしたことは、特に必要ではない。とにかくたくさん練習して、トレーニングを受けて、それを繰り返す。そこから学ぶことができる。でも、生まれ持ったコントロールセンスがなければ、教えることが難しくなる。その点で、彼にチャンスがあることは間違いない。
──ファイナルに進出した5人と、それ以外の14人との差は大きかったのだろうか。
MH:差は、確かにあった。ドライビングと、マシンを操る技量は、かなり大きな差があった。それに、ラリー競技に対してのポテンシャルについても、多少の開きはあったね。
──今回、二次選考に進出した19人のポテンシャルは、フィンランドの若手ドライバーと比べてどうか。
MH:フィンランドでこのような選考会を行ったとしたら、フィンランドではラリーは国技同然のモータースポーツなので、氷の上で走っていたドライバーや、オートクロスやラリー経験者がものすごくたくさん参加してくると思う。応募者の全員が、何かしらのバックグラウンドや、運転経験や、趣味で走っていたりという経験を持っているだろう。さっきも言ったように、今回はモータースポーツや運転もしたことがない応募者もいた。そういう意味では、状況は異なるだろうね。
でも、全体として、フィンランドで5、6人を選んだとしても、今日の5人とレベルは似ていると思う。ここでだって、才能のあるドライバーがいたんだからね。ただ、フィンランドには、オートクロスや凍った湖を走っている若いドライバーがたくさんいるから、日本のドライバーよりもマシンの操縦スキルの基本は少し多く積んでいるかもしれないね。